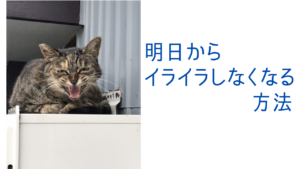「知らなかった」・・では済まされない。一般家庭の相続税

両親が70代・80代になる団塊ジュニア世代・・・そろそろ「相続」も視野に入ってくるころです。
そして、やっぱり気になるのは「相続税」
それでも「相続税は金持ち税」と言われ、「対岸の火事」「自分とは無縁」・・なんて思っている人も多いはず。
しかし!
普通のサラリーマン世代でも、思わぬところで相続税がのしかかり、「こんなはずじゃなかった・・」なんてことも。
そうならないためにも、今からしっかり「知って」おきましょう!
相続税のかかる人って?
ざっくり言えば、親が資産を「たくさん」持っている人は相続税がかかる・・ということです。
では、この「たくさん」はいくらなのか・・というと、ちゃんと計算式があります。
たくさんの資産=相続税控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の人数)
たとえば法定相続人(相続できる人)が母親と子供二人だったりすると、
3000万円+600万円×3人=4800万円・・となります。
・・なので、父親が4800万円以上の資産を持っていれば相続税がかかって、4800万円以下であれば相続税はかからない・・ということです。
(その他、細かい控除なんかはたくさんありますが、ここで簡単にするために話を省きます)
「ウチの親はそんなにお金もってないよ」
・・なんて思っていたら大間違い。
お金(現金)=資産ではないからです。
「資産」には お金の他に、家や土地の固定資産、株や債権の金融資産、骨董品や絵画・・・などなど、それらを全部ひっくるめて「資産」だからです。
・・なので、両親の住んでいる土地の評価が高かったりすると、資産が4800万円を超えて相続税がかかる・・なんてこともあるわけです。

私の友人のケースです。
友人の両親の住んでいた家の近くに新しい駅ができました。
駅ができると、その周辺の土地の評価が(一般的に)バク上がりします。
いつの間にか評価額が2倍になっていた土地を相続した友人。
しかも、父親は現金をほとんど残さないまま亡くなってしまいました。
そして、相続税は(基本的には)現金で払わなければなりません。
「たくさんの資産をもっている父親」を亡くした友人は泣く泣く100万円近い相続税を自分の財布から払うことになりました・・。
こんなふうに、現金を相続すれば、その中から相続税を支払うことができます。
でも、現金以外の資産を相続することになった場合・・先程の土地や、高騰した未上場株式
・・「評価は高いが、売って現金化できない資産」を相続するときには注意が必要です。

もう1つ。
相続の対策として親が子に少しづつ資産を「贈与」していく方法があります。
よくある方法は贈与税のかからない範囲(110万円以下)を毎年 贈与し続ける・・なんて方法ですが、ここにも落とし穴が。
まず、親が亡くなる3年前までに受けた贈与は、「相続の資産」に算入される・・ということ。
先の例でいえば、親が亡くなる前に贈与したお金の3年分(110万円×3年分=330万円)が相続財産にプラスされる、とうことです。
プラスされた結果、「たくさんの資産」になってしまえば、相続税を払うことになります。
あと注意が必要なのは110万円以下の贈与を毎年繰り返すと、
税務署から「意図的に分けて税金逃れしてるでしょ?」と見なされ、(実際そうなんですが・・)まとめて相続税の対象になったりします。
110万円の贈与を10年間くり返すと、「1100万円が相続された」と見なされ、相続税の対象になったりします。
対策としては、「定期的に同じ金額」を贈与するのではなく、時期や金額をバラバラにして「意図的」に見えないようにする・・なんていう方法があります。

・・ということで、ごく一般的な家庭でも、普通に「相続税」は襲ってきます。
いわゆる「相続税対策」はたくさんありますが、一番の相続税対策は「親と良好な関係を保つ」・・ということ。
ちゃんと話し合いができる関係であれば、今の資産状況がどうなっているのかも聞くことができるし、それがわかっていれば様々な対策をとることができます。
相続の話は親の体調が悪くなってからでは、なかなか切り出しにくいもの。
自分の両親に対して、育ててくれた恩に感謝する・・のはもちろんのこと、「自分の身を守る」という意味でも、親との関係・・大事にしたいものです。